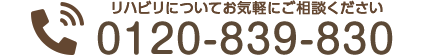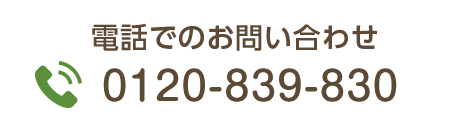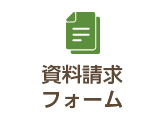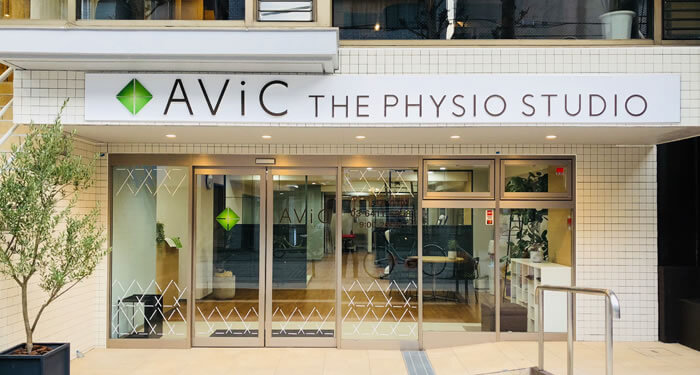【理学療法士が解説】脳性まひのリハビリ完全ガイド|筋力トレ・痙縮治療・装具療法まで詳しく紹介

症状は人によって異なり、筋肉のこわばり(痙性)、バランスの取りにくさ、動作のぎこちなさなどが見られます。
また、成長に伴い二次的な障害(関節の変形や筋短縮など)が現れることもあり、適切なリハビリを続けることがとても重要です。
一方で、どのようなリハビリが効果的なのか、どの治療法を選べばいいのかは、ご本人やご家族、医療者にとって大きな悩みとなることが少なくありません。
本記事では、脳性まひの方に対するリハビリの重要なポイントを紹介し、日本のリハビリガイドラインで推奨されている治療法についても解説します。
更新履歴
2025年3月22日
脳性まひに対するリハビリのポイントを解説
筋力トレーニング
筋力トレーニングは、日本の脳性まひリハビリガイドラインでも推奨されている重要なリハビリ手法のひとつです。適切な運動によって筋力の向上や姿勢の改善が期待できるため、歩行や日常生活の動作をスムーズにするための基礎となります。
筋力トーレニングの効果は?
研究では、一人歩きが可能な脳性まひ児を対象に、以下の運動を取り入れたところ、下肢筋力の向上や姿勢の改善が認められました。
筋力トレーニングは何をすればいいの?
- 立ち上がり訓練(スクワットなど)
- 段差昇降トレーニング
- サーキットトレーニング(さまざまな運動を組み合わせた訓練)
筋力トレーニングで注意するポイントは?
- 筋力トレーニングが歩行速度や歩幅にどのように影響するかは、まだ明確には分かっていません。
- 無理な負荷をかけると、筋緊張(筋肉のこわばり)が悪化する可能性もあるため、慎重に進める必要があります。
- 運動学習(繰り返しの動作で動きを身につけること)を意識し、日常動作に結びつくようなトレーニングを選択することが大切です。
装具療法
装具療法は、脳性まひによる歩行や姿勢の問題を改善するために重要な治療法の一つです。
特に下肢装具は、足の位置を整え、筋活動を補助し、歩行や日常生活の動作をサポートする役割を持ちます。
装具療法の効果は?
- 短期的な関節可動域の改善効果があります。
- 足首の底屈(つま先が下がる動き)を制限する装具は、歩行の改善が期待できます。
- 立位姿勢が安定することで、上肢(手や腕)の機能が向上するケースもあります。 (例:安定した立位が取れることで、食事・着替え・書く動作がしやすくなる)
装具を選ぶ時に押さえておくべきポイントは?
装具は素材や形状により、機能が異なります。目的に応じた選択が重要です。
1)プラスチック製AFO(一般的な短下肢装具)
- 軽量で関節角度を保持しやすいです。
- 変形が少ない場合に適しています。
2)金属支柱付き装具
- 足の変形が強く、硬い場合に使用される
- 保持力が高く、強い痙縮のあるケースでも安定して使用できます。
どの装具が適しているかは、使用目的や歩行パターンを考慮して決定するのが望ましいです。
ロボット療法
ロボット療法は、近年注目されている最新のリハビリ技術の一つで、脳性まひの歩行改善に活用されています。
ロボット療法の特徴は?
- 歩行をサポートし、「反復的なトレーニング」を行うことで、歩行の学習効果を高めます
- 個々の患者の歩行能力に応じて、サポートの強さを調整できます
- セラピストの負担を軽減し、効率的な歩行訓練が可能になります
詳細は下記の記事をご参照ください。
歩行支援型ロボットについてはこちら
https://www.avic-physio.com/column/id2398/
https://www.avic-physio.com/column/id2493/
Orthbotについてはこちら
https://www.avic-physio.com/column/id3197/
痙縮治療
1)経口抗痙縮薬(内服薬による治療)
経口抗痙縮薬は、痙縮を和らげるために使用される薬で、脳や脊髄の神経の働きを抑制することで筋緊張を軽減する作用があります。
ボツリヌス療法と異なり、広範囲に作用するため、全身的な痙縮の緩和を目的とする場合に用いられます。
2)ボツリヌス毒素療法(ボトックス療法)
ボツリヌス毒素(ボトックス)を筋肉に注射することで、一時的に筋緊張を緩和し、関節の可動域を広げる治療法です。特に痙縮が強く、動作が制限されている場合に有効とされています。
- 筋緊張の軽減:上肢・下肢の筋肉のこわばりの改善
- 関節可動域の改善:特に肘・手関節・足関節の柔軟性向上
- 歩行能力の向上:下腿三頭筋(ふくらはぎの筋肉)への注射により、尖足(つま先立ちのような歩き方)が改善し、歩行バランスが整う
- 手の器用さの向上:手の筋緊張が和らぐことで、細かい作業がしやすくなる
そのため、日本の脳性まひリハビリガイドラインでは「強く勧められる治療法」とされています。
一方で、痙縮が軽減すると同時に、一時的に筋力が低下することがあるため、適切なリハビリを行わないと動作が不安定になる可能性があるため専門家による評価が重要となります。
まとめ
脳性まひのリハビリテーションは、成長や生活環境の変化に伴い、継続的な調整が必要となる重要なプロセスです。
筋力トレーニングや痙縮治療、装具療法、ロボット療法など、多様なアプローチがあり、それらを適切に組み合わせることが効果的です。また、現在も研究が進められ、新しい治療法が考案されています。
リハビリの進め方や治療法について悩まれている方は、まずは専門医やリハビリの専門家に相談することをおすすめします。
個々の状態に合った適切なリハビリプランを立てることで、より良い生活の質(QOL)の向上が期待できます。
脳梗塞のリハビリTips
AViC Report よく読まれている記事