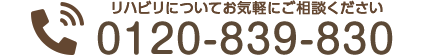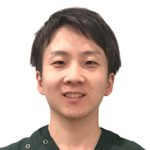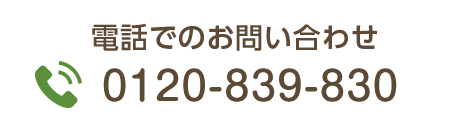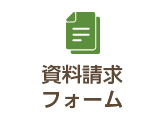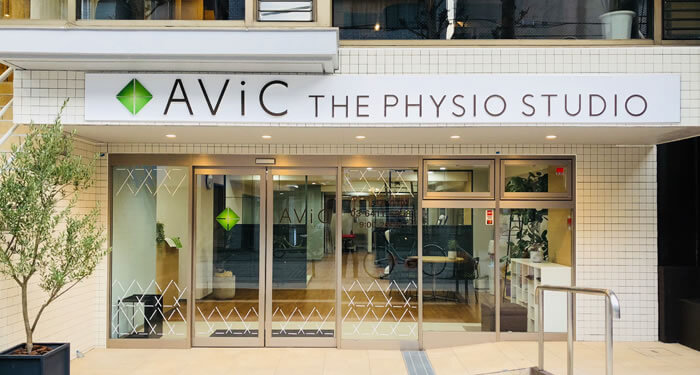脳梗塞で歩行が不安?|良くなる人の特徴とリハビリ方法を解説!

脳梗塞になっても再び歩けるようになるのか?
脳梗塞を発症すると、多様な症状が出現します。その中でも、歩行障害は代表的な症状となります。発症時に44.1%が入院時に何らかの運動障害を呈し、46.0%が歩行不能であったと報告されています[1]。さらに、脳卒中後3〜5日以内に57.9%の患者が何らかの身体的支援なしに歩行することができなかったと報告されています[1]。
発症後の経過もいくつか報告があります。発症後にリハビリテーション施設で治療を受けた患者の場合、3か月後の自立歩行回復率が60%、6か月後には65%に増加し12か月後には91%であったというデータがあります[2]。一方で、急性期病棟で治療を受けた患者の場合、12か月後で74%の回復率であり、リハビリテーション施設でのリハビリ実施の重要性が示唆されています[2]。また、早期からリハビリ(発症後24時間以内)を開始した場合、発症後3か月で75%の患者が歩行可能となったと報告されています[3]。
発症後早期では50%以上の患者が歩行困難となりますが、自然経過およびリハビリの影響で発症後6か月では60%以上の患者が歩行可能となる可能性があります。一方で、何かしらの介助が必要である可能性も高く、継続的なリハビリが必要な患者も少なくないのが現状です。
歩行が良くなったって何で評価するの?
歩行を評価するツールが数多くありますが、世界的にコンセンサスが得られている評価ツールを用いることで、自らの能力を正確に知ることができます。
以下、代表的な評価ツールを紹介します[4,5]。
- Functional Ambulation Category(FAC)
- 10m歩行テスト
- Dynamic Gait Index(DGI)
- 空間・時間的パラメータ(歩行速度、歩幅など)
- 麻痺側の脚の推進力
- Gait Profile Score
- Gait Deviation Index
これらのツールの中から、患者の状態に合わせて適切な評価ツールを選択していくことが重要となります。
歩行が良くなりやすい人ってどんな特徴があるの?
リハビリを実施する上で患者の回復を予測することは、リハビリプログラム立案や目標設定においてとても重要なこととなります。これから、脳梗塞後の歩行障害回復を予測するのに重要な因子を、いくつかの研究から紹介していきます[6–12]。
- 年齢
- 脳卒中の重症度
- 脳卒中の種類(脳梗塞か脳出血か、右半球か左半球か、など)
- 病変の大きさ
- 併存疾患の有無(糖尿病など)
- 高次脳機能障害の有無
- 皮質脊髄路損傷の有無
- 認知機能障害の有無
- 座位保持能力
- ADL能力
- 下肢筋力(股関節伸展筋力、MRCグレードなど)
- 体幹機能(TCTスコアなど)
代表的な評価ツール:TWIST アルゴリズム[6]
脳卒中後4週、6週、9週の時点で歩行自立を獲得する患者について、それぞれ86%、86%、88%の精度で予測できたという報告があります[8]。これは、理学療法士が経験のみで判断するよりも高い精度となっており、このような客観的なツールを併用することが重要となります。TWIST アルゴリズムの詳細はこちらの記事も参考にしてください
これらの要因を発症後早期に評価することで、その後の歩行能力改善を予測しやすくなります。主に急性期での情報が必要となりますので、患者およびスタッフで情報共有することが重要となります。
歩行を良くするリハビリには何があるの?
世の中には、多種多様なリハビリ手法が存在します。自分のあった手法を探すのはとても大変です。そこで、まず参考にするのが診療ガイドラインです。これは、各国で専門家と当事者がそれぞれの立場で科学的エビデンスや意見を出し合いながら、推奨を決定したものになります。まずは、脳梗塞後の歩行障害の改善に対するリハビリ手法の推奨度を知った中で、自分のあったものを専門家とともに選択することが重要です。
ここで、各国の診療ガイドラインを参考にリハビリ手法をまとめたいと思います。
以下、主なリハビリ手法になります。
- 集中的は歩行トレーニング
- トレッドミルトレーニング
- 免荷式トレッドミルトレーニング
- 歩行補助ロボットトレーニング
- 機能的電気刺激トレーニング
- 装具療法
- サーキットトレーニング
- 有酸素運動
- 筋力トレーニング
- 仮想現実トレーニング
以下の図は、日本、アメリカ[13]、オーストラリアの診療ガイドラインを比較した表になります。推奨度の設定は各国で異なりますが、色が付いている項目が最も推奨度の高いリハビリ手法になります。
これをみると、集中的な歩行トレーニングが最も推奨度が高くなっています。患者の病態や重症度に合わせて、ロボットや装具、電気刺激療法などを併用しできるだけ集中的に歩行トレーニングできる環境を整えることが重要となります。
歩行障害に対するリハビリに関しては下記の記事も参考にしてください。
- 効果的な歩行リハビリとは? 脳卒中・パーキンソン病へのトレッドミルトレーニングの効果
- 脳梗塞リハビリの新たな選択肢!ロボットリハビリとは?歩行編
- 【トヨタ自動車開発】脳卒中の歩行能力を向上させる歩行支援ロボット「ウェルウォーク」の特徴とは?
歩行改善に加え、上肢のリハビリについても知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
脳梗塞による歩行障害を回復させることは、多くの方が目標とされる大切なステップです。この記事で紹介したデータや予測は、他の患者さんのデータをもとに算出されたものであり、必ずしもすべてがご自身に当てはまるわけではありません。
しかし、リハビリは日々進歩しており、予測を超えた改善を実現される方も数多くいらっしゃいます。一つの参考として情報を捉えつつ、主治医や担当療法士と相談しながら、自分に合ったリハビリプログラムを計画していくことが重要です。
私たちの施設でも、歩行が困難だった方が根気強くリハビリに取り組み、再び外を歩けるようになった例がございます。諦めずに、小さな一歩を積み重ねることで、大きな成果に繋げていきましょう。
2025年2月25日 更新
出典
1)Louie DR, Simpson LA, Mortenson WB, Field TS, Yao J, Eng JJ. Prevalence of Walking Limitation After Acute Stroke and Its Impact on Discharge to Home. Phys Ther. 2022;102. doi:10.1093/ptj/pzab246
2)Preston E, Ada L, Dean CM, Stanton R, Waddington G. What is the probability of patients who are nonambulatory after stroke regaining independent walking? A systematic review. Int J Stroke. 2011;6: 531–540.
3)AVERT Trial Collaboration group. Efficacy and safety of very early mobilisation within 24 h of stroke onset (AVERT): a randomised controlled trial. Lancet. 2015;386: 46–55.
4)Van Criekinge T, Heremans C, Burridge J, Deutsch JE, Hammerbeck U, Hollands K, et al. Standardized measurement of balance and mobility post-stroke: Consensus-based core recommendations from the third Stroke Recovery and Rehabilitation Roundtable. Neurorehabil Neural Repair. 2024;38: 41–51.
5)Dos Santos RB, Fiedler A, Badwal A, Legasto-Mulvale JM, Sibley KM, Olaleye OA, et al. Standardized tools for assessing balance and mobility in stroke clinical practice guidelines worldwide: A scoping review. Front Rehabil Sci. 2023;4: 1084085.
6)Smith M-C, Barber PA, Stinear CM. The TWIST algorithm predicts Time to Walking Independently after stroke. Neurorehabil Neural Repair. 2017;31: 955–964.
7)Selves C, Stoquart G, Lejeune T. Gait rehabilitation after stroke: review of the evidence of predictors, clinical outcomes and timing for interventions. Acta Neurol Belg. 2020;120: 783–790.
8)Smith M-C, Scrivener BJ, Skinner L, Stinear CM. Accuracy of physiotherapist predictions for independent walking after stroke. Neurorehabil Neural Repair. 2024;38: 742–751.
9)Kennedy C, Bernhardt J, Churilov L, Collier JM, Ellery F, Rethnam V, et al. Factors associated with time to independent walking recovery post-stroke. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2021;92: 702–708.
10)Craig LE, Wu O, Bernhardt J, Langhorne P. Predictors of poststroke mobility: systematic review. Int J Stroke. 2011;6: 321–327.
11)Preston E, Ada L, Stanton R, Mahendran N, Dean CM. Prediction of Independent Walking in People Who Are Nonambulatory Early After Stroke: A Systematic Review. Stroke. 2021;52: 3217–3224.
12)Gianella MG, Gath CF, Bonamico L, Olmos LE, Russo MJ. Prediction of Gait without Physical Assistance after Inpatient Rehabilitation in Severe Subacute Stroke Subjects. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2019;28: 104367.
13)Winstein CJ, Stein J, Arena R, Bates B, Cherney LR, Cramer SC, et al. Guidelines for Adult Stroke Rehabilitation and Recovery: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2016;47: e98–e169.
脳梗塞のリハビリTips
AViC Report よく読まれている記事