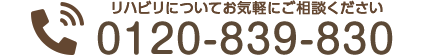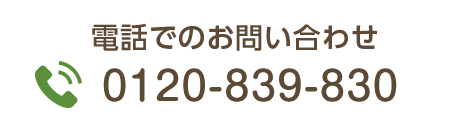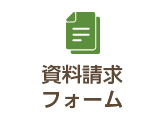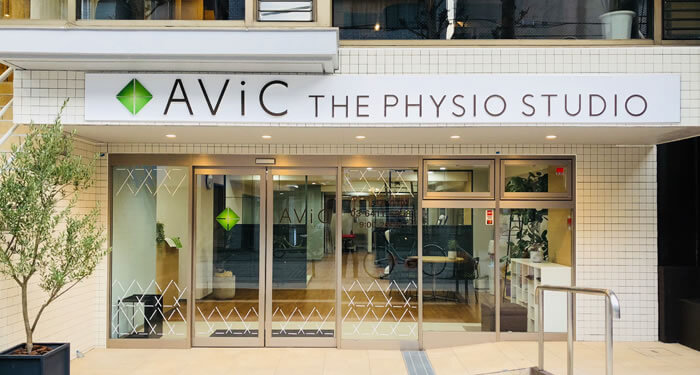脳梗塞の再発予防とは?|2回目を防ぐ効果的な方法3選

脳梗塞の再発率と再発メカニズム
脳梗塞は再発する可能性が高い病気のひとつです。今回は、脳梗塞の再発率や再発する理由、対策について見ていくことにしましょう。
脳梗塞の再発率(10年再発率)は49.7%という報告もあり(参考文献1)、これが全体に当てはまるのであれば脳梗塞を起こした約半分の方が2回目の脳梗塞を発症することになります。脳卒中は日本の死因の第4位で(参考文献2)、そのうち「脳梗塞」は最も多く57.0%を占めています(参考文献3)。再発によって亡くなる方も少なくありません。ちなみに、病気を発症してから、1年以内に再発した人の割合を1年再発率、10年以内に再発した人の割合を10年再発率と言います。
脳卒中全体で見てみると、10年再発率は51.3%という報告があります(参考文献1)。脳梗塞以外ではくも膜下出血(SAH)が70.0%、脳出血が55.6%とどの病気も高いことが伺えます(参考文献1)。脳梗塞の1年再発率は10.0%です(参考文献1)。つまり10人に1人は1年間で発症していることになります。
海外の研究ではありますが、再発を起こす時期について発症後数日から1週間が再発率が最も高いと報告しているものもあります(参考文献4)。これは、発症後の症状の変化(悪くなったりしていないか)には注意が必要であることを意味します。変化が少しでもあった場合にはすぐに担当の医師や看護師に相談することが大切です。
それでは次に、脳梗塞が再発する理由やメカニズムについて触れていきたいと思います。
脳梗塞は、原因によってラクナ梗塞、アテローム血栓性脳梗塞、心原性脳塞栓症の3つに分けることができます。
①ラクナ梗塞とは?
ラクナ梗塞は、穿通動脈(せんつうどうみゃく)と呼ばれる、脳の細い動脈が高血圧などのために損傷を受けて血栓(血のかたまり)などが詰まってしまい、発症します。梗塞はとても小さく脳の深い部分に起こることが特徴です。小さい損傷のため、脳へのダメージが少なく、症状は比較的軽いことが多いのですが、何度も再発を繰り返すとパーキンソン症候群(手の震えや足が出にくくなるといった症状)や認知症の原因になるといわれています。
ラクナ梗塞の再発率は、1 年で7.2%、10 年で46.8%と報告されています(参考文献1)。
②アテローム血栓性脳梗塞とは?
アテローム血栓性脳梗塞は、首にある頸動脈と呼ばれる太い血管の動脈硬化(アテローム硬化)が原因で起こる脳梗塞です。頸動脈は脳へ向かって血管が広がっていきます。その頸動脈が動脈硬化を起こすと血管内でできてしまった血栓がはがれて脳へと飛んでいき脳梗塞を引き起こします。最初は運動麻痺(マヒ)などの症状が軽くても、その後、徐々に進行することが多いのが特徴です。
動脈硬化は、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病が原因で起こると言われています。頸動脈の他にも、冠動脈と呼ばれる心臓に酸素や栄養を与える血管や、足の血管にも動脈硬化がみられることが多く、心筋梗塞や下肢閉塞性動脈硬化症といった病気を発症することも少なくありません。アテローム血栓性脳梗塞の再発率は、1年で14.8%、10年で46.9%と言われています(参考文献1)。
③心原性脳塞栓症とは?
心原性脳塞栓症は、心臓の中にできた血栓が脳の動脈に流れ込んだことで、脳内の血管を詰まらせることが減で起こる脳梗塞です。不整脈など心臓が正常にリズムよく動いていない場合や、心臓病(心臓の中にある弁などの異常)があると血液が滞りやすくなり、血栓ができやすくなります。心原性脳塞栓症の再発率はこの3つの脳梗塞の中で最も高く、1年で19.6%、10年で75.2%と言われています(参考文献1)。
脳梗塞が再発するとどうなる?
脳卒中において再発を繰り返すと運動麻痺(マヒ)などの症状が改善しにくくなります(参考文献5)。欧米の研究ではありますが、再発した人と1回のみの人で比べた際には、歩くことや、日常生活の活動(食事、歯磨きや洗顔などの整容、着替え、トイレに行く、お風呂、体を洗う)でより多く介助が必要になる人が増えています。認知症が悪化することも報告されています(参考文献6、参考文献7)。
脳梗塞の再発予防に効果的な方法3選
脳梗塞の再発にかかわる要因として、高血圧、糖尿病、脂質代謝異常(高コレステロール値の異常など)、喫煙、心臓病(心房細動など)などが挙げられます(参考文献8)。これらの要因を悪化させないように予防する方法としては、医師から処方された薬をちゃんと飲むこと、血圧の管理を行うこと、リハビリ(運動)を行うこと、生活習慣(食事と禁煙)を見直すことが重要です。ここでは、それぞれの方法について詳しく解説します。
①脳梗塞の再発予防と薬および血圧の管理について
再発予防のために、抗血栓薬を使ったり再発の原因となりやすい高血圧・糖尿病・脂質異常症の治療薬を医師から決められた期間は継続して飲み続けることが大切です。収縮期血圧(上の血圧)が130、拡張期血圧(下の血圧)が90mmHg以下の患者さんはそれ以上の患者さんに比べて脳梗塞の発症リスクが低いことが示されており(参考文献9)、脳卒中治療ガイドラインにおいても目標とする血圧レベルについて少なくとも140/90 mmHg未満とするよう強く勧められています(参考文献8)。
②脳梗塞の再発予防と運動(リハビリ)について
脳梗塞は血管が硬くなってしまうことが主な原因の一つです。脳梗塞後の患者さんでも運動をすると血管の機能がよくなることが分かっています(参考文献10)。また、脳梗塞の再発の原因となる糖尿病や脂質異常症も、運動により改善すること可能性があるため(参考文献11、参考文献12)。普段の生活から運動を取り入れてみるのも良いかもしれません。
具体的には、無理のない範囲で中等度強度の有酸素運動を少なくとも週4日以上各10分程度、合計で週150分程度行うか、あるいは高強度の有酸素運動を週2日以上各20分程度行うことが推奨されています(参考文献13)。ウォーキングや早歩き、階段の上り下り、エアロバイクなどを組み合わせることで大切です。
もっとも、脳卒中による麻痺など後遺症により運動が困難な場合もあるため、そうしたケースでは監督下リハビリテーション(理学療法士による運動指導など)を通じて安全に身体活動量を確保する工夫が重要です。
③脳梗塞の再発予防と生活習慣について
・食事に気をつけよう
食事においては、過度な塩分摂取を控えたり、脂っこいものを適度に制限するといった一般的に言われていることを守ることが大切です。目安としては1日あたり食塩摂取量を1g以上減らすだけでも再発リスクを下げるのに有用とされています(参考文献13)。具体的には、1日4g以上の塩分を摂る人は1.5g以下の人に比べ脳卒中リスクが2.6倍になるという報告もあります(参考文献13)。
また、近年では野菜や果物を中心とした食生活や地中海食が注目されています。地中海食とは、魚やオリーブオイル、ナッツなどの一価不飽和脂肪酸や植物性食品を多く含み、赤身肉や飽和脂肪を控えめにした食事パターンです。その程度については、医師や管理栄養士の指導を受けるようにしましょう。
・喫煙について
脳梗塞に関連する生活行動の1つに喫煙があることは比較的有名かもしれません。禁煙することで脳梗塞を発症する危険性は低くなります。最近では、禁煙外来なども耳にするようになってきました。体調管理で気になる方は一度検討してみてはいかがでしょうか。
・飲酒について
飲酒は、適度な量を把握することが大切です。スウェーデンの研究では、純アルコール量で約20g程度が脳梗塞のリスクが高まる1つの境目と報告しています(参考文献14)。これは、ビールで中びん1本(500mL)、日本酒で1合(180mL)、焼酎で0.6合(約110mL)、ウイスキーでダブル1杯(60mL)、ワインで1杯(120mL)に相当します。
・サプリメントについて
脳梗塞に対するサプリメントの影響について詳しいことはわかっていません。現状としてはサプリメントの摂取は推奨されるまでの根拠がないようです。サプリメントはあくまで補助的なものであり、過剰摂取に注意する必要があります。普段の食事から気をつけることが大切です。
まとめ
今回は、脳梗塞の再発に焦点を当てて、再発率や再発予防法について紹介しました。脳梗塞は再発率が高い病気ですが、しっかりと危険な要因を理解して、再発を予防することが大切です。
2025年2月27更新
出典
1. Hata J, et al.:Ten year recurrence after first ever stroke in a Japanese community: the Hisayama study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2005; 76(3): 368-72.
2. 厚生労働省:平成28年(2016)人口動態統計(確定数)の概況、性別にみた死因順位(第10位まで)別死亡数・死亡率(人口10万対)・構成割合
3. 厚生労働省:平成28年(2016)人口動態統計(確定数)の概況、死因簡単分類別にみた性別死亡数・死亡率(人口10万対)
4. Oza R, Rundell K, Garcellano M. Recurrent Ischemic Stroke: Strategies for Prevention. Am Fam Physician. 2017 Oct 1;96(7):436-440.
5. 輪田 順一ら:脳梗塞例の長期予後と再発作―久山町18年間の追跡調査―. 脳卒中. 1983; 5: 124-30.
6. Ng YS, et al.:How Do Recurrent and First-Ever Strokes Differ in Rehabilitation Outcomes? Am J Phys Med Rehabil. 2016; 95(10): 709-17.
7. Mizrahi EH, et al.:Functional gain following rehabilitation of recurrent ischemic stroke in the elderly: experience of a post-acute care rehabilitation setting. Arch Gerontol Geriatr. 2015; 60(1): 108-11.
8. 日本脳卒中学会:脳卒中治療ガイドライン2021[改定2023]、株式会社協和企画、2023
9. Thomopoulos C, et al.:Effects of blood pressure lowering on outcome incidence in hypertension: 2. Effects at different baseline and achieved blood pressure levels–overview and meta-analyses of randomized trials. J Hypertens. 2014; 32(12): 2296-304.
10. Takatori K, et al.:Effect of intensive rehabilitation on physical function and arterial function in community-dwelling chronic stroke survivors. Top Stroke Rehabil. 2012; 19(5): 377-83.
11. Umpierre D, et al.:Physical activity advice only or structured exercise training and association with HbA1c levels in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. JAMA. 2011; 305(17): 1790-9.
12. Kelley GA, et al.:Effects of aerobic exercise on lipids and lipoproteins in adults with type 2 diabetes: a meta-analysis of randomized-controlled trials. Public Health. 2007; 121(9): 643-55.
13.Bangad A, Abbasi M, de Havenon A. Secondary Ischemic Stroke Prevention. Neurotherapeutics. 2023 Apr;20(3):721-731. doi: 10.1007/s13311-023-01352-w. Epub 2023 Mar 6.
14. Larsson SC,et al.:Differing association of alcohol consumption with different stroke types: a systematic review and meta-analysis. BMC Med. 2016; 14(1): 178.
脳梗塞のリハビリTips
AViC Report よく読まれている記事